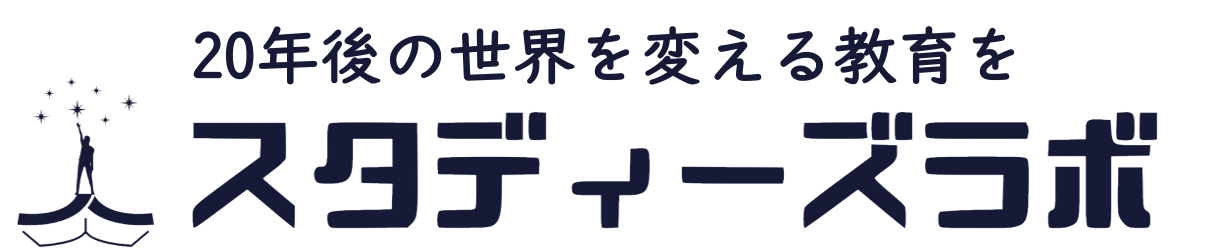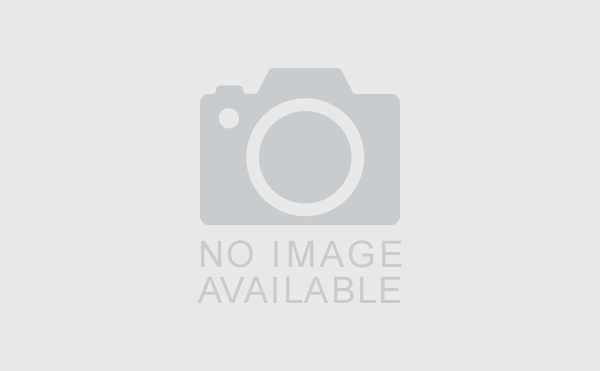広尾学園中学・徹底攻略【理科】
広尾学園中学の理科は、年度にかかわらず、非常に解きごたえのある良問ぞろいのテストです。
基礎的な知識をしっかり身に着けたうえで取り組めば、中学や高校で習うような発展的な内容の理解を深めることができるので、理科に興味のある受験生は、腕試しとして、時間を測らずにじっくりと全文熟読しながら取り組んでみてほしいです。
ただし、広尾学園に受験を考えている場合は、時間感覚を身に着けるためにも、時間を測って読み飛ばして取り組みましょう。
読み飛ばしへの考え方
前述しましたが、文章量が非常に多いので、読み飛ばして取り組むことがほぼ必須のテクニックになっています。
中学や高校で習うような発展的な内容を小学生の推論で答えに導くために、非常に丁寧にレールを敷いてくれています。
その分、全体の文章量が多くなっているというわけですね。
理科の問題では、国語の問題のように、問題が最後にまとまっていないので先に問題だけ読むことは少し難しくなっています。
しかし、先に問題だけ読むというテクニックは相変わらず非常に強力なものとなっています。
敷かれたレールの行き先がわかっている状態とわかっていない状態では文章への向き合い方から変わってきます。
また、基礎のしっかりしている分野と基礎の荒い分野では、読むスピードから変わってきます。
レールにしっかり乗るためにも、基礎を鍛えて読むスピードを上げておきたいですね。
勉強方法・過去問への取り組み方
生物・化学・物理・地学のどれかが出やすい、出にくいといった傾向はあまり見られません。
しかし、すべての分野に共通して言えることがあります。
それを以下にて詳しく解説します。
基本用語・基礎知識
基本用語を直接問われる問題は毎年1~2問と、数こそ少ないですが、教科書に載っているような知識はすべて前提として扱われます。
「小学生でもできる推論で」と前述しましたが、この推論で使うのが教科書の知識です。
基本的な内容の問題にも取り組み、苦戦しないレベルまで仕上げましょう。
実験・観察、考察
最も設問数が多く、最も差のつく最重要課題となります。
実験・観察を通じて考察を促し、考察内容を択一で選ばせるだけでなく記述の問題も多く出題されます。
対策については後述します。しかし、重要なのは択一問題です。
大門ごとに、この実験を通じて、最も興味深い・知ってほしい内容への設問がおおむね最終問題にあり、択一問題になっています。
択一問題は最終問題に限らず、「小学生でもできる推論」で記述させるには難しすぎる考察を行うためにもよく出題されます。
ここを〇分の1当てた!などといった取り組み方をせずに、実験から何を読み取るべきだったか、そこからどう考えればよかったのかまで深く追及する復習をおすすめします。
特に2分の1まで絞れたけど外した!といったときはチャンスです。仮説を立てる練習台にしましょう。
また、毎年多くの設問で、表やグラフが用いられます。
これらを読み取る力は必須となります。
増えているのか減っているのか、増え方はどうなっているか。そこから一歩踏み込んで、何がわかるのか、計算に活用できるか。しっかりと深いレベルまで理解しておきましょう。
計算問題
レベルの高い、ただ与えられた数値を四則演算しただけでは解けない構成になっていることが多いです。
与えられる数値も、問題によっては表形式で与えられ、使うべき数値を選び出す、択一問題のような能力も求められます。
本文中で与えられた、初めて聞く用語の意味をしっかりと理解しておく、与えられた公式を活用する練習をしておくことが大事でしょう。
小手先のテクニックとして、小数点の位置で計算ミスに気付くことができます。
あくまで今のところですが、「小数第二位を四捨五入して小数第一位までで答えなさい」と書かれている場合、小数第一位は0以外の数字になります。
例えば「小数第二位を四捨五入して小数第一位までで答えなさい」とあるとき、5.0が答えになることはないです。
ただし「小数第一位を四捨五入して整数で答えなさい」と書かれている場合は、50が答えになることもあります。
(把握漏れでしたらすみません)
記述問題
一口に記述とまとめてしまっても難易度は様々で、どこかの問題集で見たことのあるような基本的な問題から、教科書に載っていない内容について考察させる難しい問題まで様々です。
難しい問題では、小手先のテクニックや暗記だけでは太刀打ちできないものもあります。あえて実験に不備を残しておいて指摘させたり、本文で説明された現象の理由を考えさせたり、深い思考力が必要になります。
その分、答えがひとつでない問題もあります。
まずは、すべての問題がそういった深い思考が必要な問題ではないことを意識して、空欄を埋める意識を持ちましょう。
そして、理科を得点源と考えている場合は、理由を考えて当てていく練習をすることになります。
練習方法としては、過去問演習では、択一問題で考察の絞り方を学んだり、記述問題の別解を考えてみたりするのが効果的でしょう。